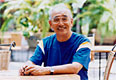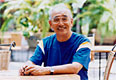|
 奥田のコラム(NO157) 第19回・帯津良一先生健康講演会in沖縄(その2) 奥田のコラム(NO157) 第19回・帯津良一先生健康講演会in沖縄(その2) | ( 2012/09/08 ) |









| 
ー沖縄養生塾・塾生による太極拳発表会ー
第19回・帯津先生健康講演会の第2部は、今回初めて沖縄養生塾の生徒さん達による気功・太極拳をプログラムの中に入れさせていただきました。
短期間ながら、日頃の姿を帯津先生に見ていただこうと、張り切って練習に励みました。 帯津先生の目の前で、誰もが全身を震わせながらの演舞でしたが、それだけに、一生の思い出に残る記念すべきステージになったに違いありません。出演者全員の名前をここに記して、思い出の証にしようと思います。
1、浜辺の歌(てぃるる初級クラス・豊見城教室・あやかりの杜教室・名古屋教室)
越智和枝・新垣長紀・上津敏・新城廣子・中村和子
垣花美恵子・大城チズヨ・大見謝与美子・潮平慧子
大城丈典・福地みどり・石原妙子・チャーチ弘美
大城孝志・大城奈緒美・横山茂美
(リーダー:奥間・名渡山・羽地・喜納・奥田)
2、花(てぃるる中級クラス)
山城政仁・小波津仁一・小波津恵子・眞栄田輝・大城節子
上地政子・上地京子・喜友名愛子・垣花智子
金城富子・正木純子・比嘉栄子・仲地成子・西平敏彦
渡嘉敷喜美子・喜屋武すま子・島袋加代子・惣慶美智子
(リーダー:三枝・奥田)
3、四つ竹(おもろまち教室)
平田貴子・平田晴男・国吉万里子・金城信子・比嘉實勝
秦一雄・西平敏彦・幸喜健・与座圭子・三枝憲和
(リーダー:三枝・羽地・奥間・高良・奥田)
4、とーがにあやぐ(宮古島教室)
平山律子・塩川正子・池間キヨ・伊計悦子・親泊まり子
下地直子・下地真喜子・木下美津子・西崎緑
5、森の下で(あやかりの杜教室)
重田弘文・重田世公江・玉城康雄・玉城秀子・渡久山綾子
喜屋武馨・喜屋武すま子・真謝保久・玉元晴美
比屋根正美・松野耕平
(リーダー:三枝・重田・渡久山・名渡山・大里)
7, 内養功(指導者養成クラス)
三枝祥子・奥田泰子・奥間愛子・重田世公江・渡久山綾子
名渡山陽子・羽地直子・喜納一技・高良一實・大里恵理子
(リーダー:奥田清志)
* 残念ながら都合により当日参加できなかった方
植田美代子・喜屋武ヨリ子・上原邦男・宮城美紗子
徳元タケ子・金城文子・ 知念節子
<敬称略・順不同>
8、香功(シャンゴン)(全員参加)
9, 新呼吸法「時空」 (全員参加)帯津先生指導
帯津先生の総評:
沖縄養生塾の太極拳は、それぞれの教室がそれぞれの個性に溢れていて、実に興味深いものがありました。常識的には、なるだけ一糸乱れぬ太極拳を目指すのが普通でしょうが、個性あふれる沖縄の太極拳に心打たれました。
私としては、これからも、沖縄は大いに沖縄の風を感じさせてくれる太極拳を目指して欲しいと希望します。(談)
お客様からの言葉:
沖縄の古典音楽と太極拳のコラボレーションには驚きの感動がありました。宮古島の¨とーがにあやぐ¨の太極拳や、“四つ竹¨の太極拳にも感動の涙が溢れました。
沖縄の古典音楽の持つ素晴らしさに改めて誇りを持ちました。そして一生懸命に太極拳を舞う人の姿はとても美しいと
思いました。
奥田代表の言葉:
沖縄に40年も住みついていると、いつの間にか沖縄の色に染まり、それをまた喜んでいる自分がいる事に気付かされます。 私が心より敬愛してやまない(故)楊名時先生の太極拳を根底におかせていただき、それに加えて、私が感じるままの¨沖縄の風¨を身心に受け止めながら、沖縄ならではの太極拳を目指してみたいと思っている昨今の私です。
・出演者の皆さん、本当にご苦労様でした。
・帯津先生、心よりお礼申し上げます。
・観客の皆さん、沢山の応援、心から感謝です。 (2012年9月8日の記)
写真上:四つ竹の演舞
写真中:とーがにあやぐ演舞
写真下:全員参加の香功(シャンゴン) | |  |