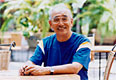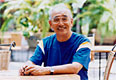|
 奥田のコラム(NO95) 帯津先生と行く内モンゴルの旅(その1) 奥田のコラム(NO95) 帯津先生と行く内モンゴルの旅(その1) | ( 2010/09/11 ) |









| 
帯津先生が2年に一度訪れておられるモンゴルの旅に、今年は我が沖縄養生塾から4人の塾生が参加してくださいました(8月上旬)。それぞれに深い感銘を受けられたようですので、今回と次回のコラムには、4人の方々の貴重な旅の感想文を載せていただく事に致しました。
(Ⅰ)虚空との出会いー内モンゴルへの旅 沖縄養生塾生 玉城 康雄
自然は二つに大別できる、という。目に見える自然と目に見えない自然。目に見える自然の奥に測り知れない力を持つ、目にする事の出来ない大いなる自然が潜んでいるのではないか。
今回の「帯津先生と行く中国内モンゴルの旅」では、その事を深くかみ締める機会になりました。
見晴るかす大草原の果てに天と地、自然の織り成す存在の深みを実感した。特に、ホロンバイル大草原は、帯津先生が多くの著書の中で語る<いのちの故郷・虚空>を体感させる場だと思いました。
よく「旅が楽しいのは、帰る家があるからだ」と言います。虚空という魂の故郷に大草原で出会い、いつか来る<いのちの旅立ちの日>が気負うことなく静かに迎えられそうです。古稀も過ぎ、初めて、かかる人智の及ばない崇高なる場にたたずむ事が出来、こころ踊る想いでした。1986年以来、2年ごとに内モンゴルを訪れている帯津先生の一途な思いが解かりかけて来ました。
今回の旅は、自己との対話、虚空との対話へと繋がるものでした。このような得がたい旅にお誘いいただいた事に深く感謝いたします。有難うございました。
(Ⅱ)ホロンバイル草原の河笑まう
沖縄養生塾生 玉城 秀子
地図上はすぐそこながら、北京経由、まる二日掛りで到着した遥かな地・内モンゴル。「帯津先生と行く中国内モンゴルの旅」は、全国各地から総勢44名が参加、天下の養生塾に相応しく熱気に満ちた旅団となった。
モンゴル到着後の旅は、草原歓迎式とモンゴル料理のおもてなしで始まり、遊牧民との交流。凍えつつも楽しんだゲルでの宿泊。森林公園での野の花たちとの出会い。胡琴や鼓など民族楽器を駆使した歌舞への招待など盛りだくさんであった。帰途登頂した万里の長城では権力の底知れなさを思い知らされた。振り返って見れば、どれも「一期一会」を言葉ではなく、魂で実感した豊かな出会いでした。
その中で特に印象に残っているもの。それは内モンゴルで最も美しいと言われているホロンバイル大草原の小高い景点から眺めたモルゲル河の佇まいであった。
河は天と地に抱かれ、草原限りない中をくねりくねり、行きつ戻りつ静かに笑まっていた。草原と共に生きている河。草原の生きとし生けるものを生かし背負っている河。しかし、河にはその気負いがない。悠久の時空の中でゆったりと、ただ在る河。それは「行く川の流れは絶えずして・・・」
に見る、流れ移り行く日本の川とは異なる。モンゴルの大自然と民族の営みにふさわしい、全てを受け止め癒していく母なる河の姿であった。観るものをも清謐にさせる気品がこの河にはあった。
「欲少なく生きているモンゴルの民の存在そのものが詩である」と司馬遼太郎は語っているが、私はモルゲル河そのものがまさに詩だと感じた。
緑の風を受けながら河と相対した小一時間。河は何も言わない。ただ微笑んでそこに在るだけだった。しかし、私の内の捉えようのない何かが静かに動き出していく時間となった。モンゴルから戻って早一月。河は今も私の中で笑まい、私を少しずつ変えている。
写真は内モンゴル・ホロンバイル大草原の風景
撮影:伊禮 洋代さん | |  |