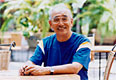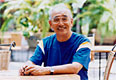帯津先生「時空」の実演


「時空」を実演する会場参加者の皆さん


「時空」を実演する参加者の皆さん


第1班・太極拳演舞「浜辺の歌」


第2班・太極拳演舞「かぎやで風」


第3班・太極拳演舞「四ツ竹」 | 
前述のコラム(NO280)では,帯津先生の近況報告と健康長寿についてのお話を要約してお伝えしましたが、今日はその講演会の第2部で演じられた2つの出来事についての報告をさせていただきます。
第2部(その1):新呼吸法『時空』の講演
帯津良一先生が帯津三敬病院の名誉院長であられる事は広く知られている事ですが、実は帯津先生は呼吸法の大家でもあられるのです。
日本には丹田呼吸法として有名な「調和道協会」という会が、長年に渡って続いておりますが、帯津先生は近年までその協会の3代目の会長を務めておられました。
帯津先生はご自分のお医者さんとしての体験と、調和道協会での体験を通して、『時空』という新呼吸法を考案され、その普及活動にも努めておられます。
新呼吸法『時空』の基本的な考え方は、大自然、大宇宙の持つエネルギーを意識の中心に置き、それらを全身に巡らせる”全身呼吸”という事になるのではないか・・・と私(奥田)は理解しております。いささか自己流ながら私は日々にこの全身呼吸を心掛けているのですが、今の所これに優る健康長寿法はない、と思うようになっております。
* 新呼吸法『時空』に関心をお持ちの方は、帯津先生ご指導によるDVDも出版されておりますので、下記のところにお問い合わせされると詳しい事が解るのでは・・・と思います。
問い合わせ先:はなまるげんき事務所/0120-343-593
(受付時間10時~17時/土・日・祭日を除く)
第2部(その2):沖縄養生塾生による沖縄発養生太極拳の演舞
帯津良一先生の健康哲学に学びながら、日頃の健康づくりを目指している沖縄養生塾「天遊会」の会員は、現在80名程いるのですが、その中から今回は40名程の方々が、3班に分かれて今回のステージに立たれました。
第1班:太極拳初級(9式)音楽はスーザン・オズボーンさんの“浜辺の歌”
第2班:太極拳中級(11式)、音楽は日出克さん編曲による“かぎやで風”
第3班:太極拳上級(24式)、音楽は日出克さん編曲による“四ッ竹”
私達沖縄養生塾「天遊会」が特に力を入れている点は、“沖縄音楽による太極拳”を目指している事であります。沖縄の古典音楽、“かぎやで風”、“四つ竹”による太極拳を発表しているのは、沖縄の永い歴史の中でも私達が初めての事ではないかと、私達は自負しているところであります。
我らが健康人生の恩師である帯津先生も、“沖縄の風”を感じる太極拳を沖縄から世界に発信する事に大きな期待を寄せてくださっているのですから、私達も大いに頑張らねばならないのです。皆さんよろしくお願いいたします。
2018年6月26日の記(82歳の誕生日)
|