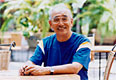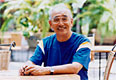|
 奥田のコラム(NO142) 沖縄の薬草料理を楽しむ会(その1) 奥田のコラム(NO142) 沖縄の薬草料理を楽しむ会(その1) | ( 2012/04/30 ) |









| 
4月から5月にかけての大連休の初日(4月28日)、私達夫婦は思いもかけないお誘いを受ける事になりました。そのお誘いというのは、沖縄本島北部にある標高500m
程の八重岳に登り、近辺に自生する薬草を摘み採り、且つ自分達でそれを料理して食べるというお誘いです。
この会を主催されたのは「沖縄瞑想の会」の方々ですが、私も家内もこのお誘いにはすっかり乗り気になり、この日は朝早くから目をさまし、嬉々として八重岳に向かって車を走らせたのです。
八重岳は日本で一番早く桜が開花する¨桜の名所¨として有名なところです。実は私はこの八重岳には16年前の忘れられない思い出があり、今回の¨八重岳で薬草料理を楽しむ会¨の参加には、その時の思い出も重なっての参加でした。
16年前、私は沖縄から北海道宗谷岬までの3,000キロを、桜の開花に沿って走る「日本列島さくら駅伝3,000キロという計画に賛同し、メンバーの一人に加わったのでした。3か月余りをかけて、無我夢中で宗谷岬に到達したのですが、その出発点となったのがこの八重岳の中腹にある¨さくらが丘公園¨だったのです。(コラムNO120に記載)。
当時私のイメージのなかにあった八重岳は、¨桜の名所¨というこの一点だけに絞られていたのですが、今回の¨薬草料理を楽しむ会¨で集合した地点は、桜とは殆ど無縁の、むしろ八重岳の頂上に近い場所にあって、そこには八重岳の別の顔があったのです。
この場所には、上地流空手の開祖、上地完文翁が修行の場とされた屋敷跡があり、その跡地に今は小さな教会が建っておりました。朝日と夕日が拝めるという八重岳の頂上(いただき)には素朴な十字架が置かれ、私はこの八重岳の頂上に強い聖地の空間を感じない訳にはいきませんでした。
さて、¨薬草料理を楽しむ会¨に集まった20名程の人達は、自分達で採った薬草を、丁寧に選別し、2時間余りをかけて料理し、その料理の全てが教会のテーブルに並べられた時は、思わず感嘆の声を発してしまいました。自然の恵みの素晴らしさに感謝の手を合わせたのです。
(2012・4・30の記)
写真上:薬草料理を楽しむ会に集まった人達
写真中:八重岳薬草料理の数々
写真下:教会内での試食会 | |  |